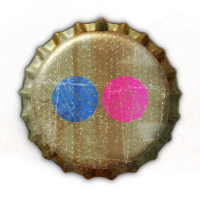社会的弱者となりやすいHIV陽性者と身 体障害者の収入向上のために、石鹸作りのノウハウを学ぼうというものである。HIV陽性者は私の 配属先が組織しているNGOメンバー、身体障害者はセントラル州にいる18年度3次隊の隊員の配属先 NGOメンバーであり、あと残りの任期で少しでも彼らの収入向上活動が起動にのれば・・・と思う 。。隊員が教えるわけではなく、すでに石鹸作りを仕事としているガーナ人講師を招き、隊員も一 緒に学ぼうという企画。
ガーナのローカル石鹸の作り方を学ぶと共に、普段認識を持って接するこ との少ないHIV陽性者や身体障害者との活動を通して、自身のバルネラブルグループに属する人々 に対する意識をみつめる機会にもなり得ると思っている。
その前に、もう少しHIV&AIDSに関する勉強をする必要があると思い、参加する予定の隊員を対象 に特にAIDSに対する差別偏見に焦点を当てたワークショップを行った。私がガーナに来る前に受け た研修の中から、比較的分かりやすい、そして私でもファシリができそうな4つのワークを少しア レンジして実施。
ファシリテーターというのは、やっぱりなかなか難しい。
日本人対象なのでもちろん日本語で行っ たわけだが、知識を学ぶワークショップとは違い、特に差別や偏見についてはいろんな気持ちや考 え方を持った人がおり、ファシリテーターとしてそれらを否定せず、受け止めること、その上で伝 えたい事を伝える、考える機会を提供するというのはなかなか簡単ではない。参加してくれた人に 自分の中に潜む、普段は考えることの少なく気が付きにくい気持ちと向き合ってもらえただろうか 。ワークの中で言ってもらった感想や意見などに、適切に対応できたかどうかは分からないけど、 できるだけ丁寧に対応するよう努力はしたつもり。
いずれにしても、私にとっては良い経験となっ た。私の英語力では微妙なニュアンスが伝えられなかったりするので、ガーナ人相手には難しいか もしれないけど、機会があったら、またこういうのもやってみたい。
昨年12月からいろいろあった大統領選挙は決選投票の結果、野党であるNDCが勝利。私の任地のあるAshanti州はクフォー前大統領の出身地のため与党NPP支持者が8割を超えるため、選挙結果にみんなガックリ肩を落としていたが、特に何か暴動が起こることもなく、無事7日に大統領就任式執り行われ、ミル大統領へと政権交代した。
日本にとって大切な貿易相手国であり、また野口英世が黄熱病の研究をしながらその命を落とした土地でもあるガーナと友好関係を築くのは重要。
2001年にも当時総理だった小泉さんが来ガーナしていることもあり、今回新大統領就任のお祝いにもまた小泉衆議院議員が来訪。8日、日本大使館にて、小泉元総理とクフォー元総理にお会いする時間がとられた。
「野口英世アフリカ賞」という賞を作ったのが小泉さんというのは知らなかったが、それについての演説を聞き、その後歓談、写真撮影など2時間くらい。その日は偶然にも小泉さんの誕生日だったので、みんなでハッピーバースデーを歌ったり^^;テレビを通じてしか見たことのない小泉さんのイメージと本物はけっこう違ったが、ちょっとミーハー的な協力隊員にも愛想よく対応してくれ、優しい雰囲気の方だった。
クフォー元大統領はさすが大統領を8年務めただけあって、その貫禄はしっかりあった。でもスピーチの中で、日本に対する援助を求める内容があって、国家の頭である大統領だった人もボランティア相手のスピーチでそういうことを言うんだなぁ…(まぁ、私たちにというよりはその場にいる小泉さんや大使館の人にも言ってたと思うけど)っていうことに少し残念な気がした。
短い時間だったけど、普通ならなかなか見ることさえできない方々とお会いできたのは、貴重な体験でした。
去年の話。
12月26日、孤児のNGOのスタッフと子どもたちと一緒にクリスマスパーティーと称して、うちの郡にあるダムに遠足に行ってきた。トロトロをチャーターし、ちょっと気分は引率の先生。滅多とない村から外出に子ども達は大はしゃぎデシタ^^
NGOの名前とマークが入ったTシャツ。子ども用の黄色シャツには「ORPHAN」(=孤児)と胸にデカデカと書かれている…これを「このために作ったんだ!いいでしょ!?」と見せられた時には、私的には「う…うん…」っていう感じだったけど、ガーナ人スタッフが何とも思わないなら、何も言わないでおこう。。
Ashanti州にはダムが2箇所あるらしく、そのうちの1つが私がいる地域にある。ガーナは水力発電に頼っているので、ダムの働きはとても重要。日本のダムは外側からちらっと施設を見られるくらいだけど、ここはさすがガーナ。落ちたら怪我どころじゃ済まないんじゃ…(><)というような場所まで通って、ダム施設を一通り見せてもらった。一応家庭の水道に通っている水はダムの水をろ過し、2種類の化学薬品によって消毒されているらしい。ま、それでも水道水なんて現地の人でも飲まないから、消毒と言っても、どこまで管理されているのかはよく分からないけど。ってか、何日も続く断水をどうにかしてほしー…
ダム見学の後は、広場でサッカーをし、フライドライスwithチキンとダンスのガーナ流お決まりパーティ。普段チキンなんて、なかなか口にできない子ども達。嬉しそうに頬張っていました。なんと私にもサプライズのプレゼントが用意されていた。ケンテというガーナの織物とクリスマスカード。ガーナ人にプレゼントされるなんて初めてで感動した☆
私がこのNGOと関わるようになったのは2008年の1月~なので、子ども達やNGOスタッフと一緒に過ごすクリスマスは今年が初めてであり、最後でもある。関わっているスタッフ全員がボランティアで成り立っているこのNGO。配属先の人とは違った通じ合う気持ちがあると思う。楽しい時間を過ごせた1日だった。
ボランティアのNGOスタッフ
2007年*ガーナに来た年
2008年*ガーナにどっぷりな年。もうけっこう充分満喫…
2009年*ガーナから帰る年!!!
てな訳で、今年の前半はガーナで、後半は日本でよろしくお願いします。
帰った後の進路についても、そろそろ真剣に考えないといけない。ガーナに来てからも母子保健に関わって仕事をしているけど、やっぱりこの分野に興味があるし、お産を見る度に助産師という仕事っていいなと思える。国際協力をいざ現地でやってみて、遠い日本からただぼんやりと眺めているのとは違い、この社会の裏表も垣間見て、「協力」という一言では表せれない事実なんかも見えたりした。仕事をするのと旅行をするのとでは大きく違うということをよーく実感して、今回の協力隊では限界を感じる部分も多々あったけど、でもやっぱり発展途上国っていうのは何だか好きで、国際協力というものの端っこでも良いからつながってたいかなというのが、今の気持ち。
自分の技術をもって、もう一度このフィールドで貢献できたらベストだと今は思えるので、とりあえずは自分の助産師としてのスキルアップに努めるつもり。帰ったら日本の病院で助産師として働き、きっと結婚、出産なんかで数年は日本にいると思う。自分の仕事に少し自信が持てるようになったら、余裕が出てきたら、もう一度「国際協力」「開発」…テーマはまだ全然考えられてないけど、院などに行って勉強し直してもいいかな。そして将来的にはNGO等で働くのが良いのかな… と自分の将来設計を考えてみたりしている。
結婚、育児、仕事の両立はそう容易くないだろうし、まだまだ考え途中、これからどんなことが起こるかも分からないから、フレキシブルに色々考えていきたいとは思っている。あとガーナでの活動も5か月、自分なりの今後の進む道が見えてきた気はしている。
JICAと相談した結果、10月にHIV陽性者の声を集めた冊子「VOICE」の製本が決まり、先日ようやく完成した。
ガーナ、ホントに時間通りに事が進まない。。約束した期限を5回以上は裏切られ、12月上旬にセネガルで行われた国際会議にも完成版が間に合わず、試作版で発表され、12月半ばも過ぎてようやく完成。ここまでの道のりが長かっただけに、完成版を手にすることができて感激☆
…と言いたいところだが、中を見て、印刷の粗さにガーナならこの程度で納得するしかないのか…とちょっと肩を落としたり。。
まぁ、でも完成は完成です。18年度3次隊の隊員と2人で製作、編集してきた物なので、わが子のような感じで、それがが形になるってのはやっぱり嬉しいものデス。
作成に当たって、一部のHIV&AIDSの専門家からは厳しい意見を頂いた。日本でも目にするこの類の冊子が、そう簡単に作成できるものではないこと、たくさんの手記から吟選され、この言葉はどうか、この表現で何が伝わるか等、熟考した上で作成されるという面では、私たちが作成した物はあまりに陳腐なものかもしれない。素人に毛が生えた程度の隊員レベルで作れるものではないと言われたとしても仕方ないが、ガーナで使われている言葉、陽性者の声をそのまま掲載することで伝えられるガーナの現状、私たちがいる草の根レベルだからこそ出来る活動があると思うので、あえてプロに頼らず自分たちとガーナ人で作り上げた。
これから活動でこの冊子を有効活用していくことを考えなければならないが、予算の関係上、量産はできず、400部ほどしかないので、そこらへんのパンフのように誰にでもポイポイあげられる訳ではない。HIVテストを受けられる施設、病院の外来、学校、HIV関係のNGOなどで活用を考えて、エイズ対策隊員だけでなく、その他医療関係の隊員や学校隊員、村落開発隊員など希望者にも活用してもらう予定。
私もさっそく今週実施していたモバイルVCTで活用してみた。HIVテストを受ける順番を待っている人々(英語なので読める人のみ)に渡してみたところ、やはりHIV陽性者の生の声を聞く機会というのは相当ないよう(村レベルでHIV陽性であることを公開している人は皆無に等しい)で、真剣に読んでくれている人もいた。中には、テストを受ける前にHIV&AIDSの説明をしている段階で、「そんなのクマシとかアクラとか都会の話で、こんな田舎にはいないよ」と言う若者もいて、彼にもVOICEを読んでもらい、自分と同じように、誰かの親であったり、誰かの夫、妻であったり、誰かの子どもがHIV陽性であること、決して特別な人だけが感染しているわけではないことを知ってもらった。
この本を通じて、真剣にHIV陽性者のことを考えてくれる人は少ないかもしれない。でも読むだけでも良い。ちらっとそういう人たちが存在していること、どういう気持ちを抱いているかを知ってもらうだけでも良いと思っている。ちょっとだけでも読む前より、その人のHIV&AIDSに対する気持ちが変わってくれれば、それだけで意味はあるだろうし、そういう機会をこの本によって与えられれば作った甲斐がある。