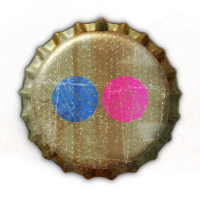3月にこのブログでも書いたワークショップ。
上司と何度と話し合った結果、実現したいしその必要性も感じる。
しかし、私の配属先Atwima Nwabiagya郡GHSの今期の予算は約3万円。
ガーナ、いくら物価が安いとは言え、日本で言えば県の保健所に当たる機関の予算が3万円って…。予防接種をするために車でしか行けないようなコミュニティーにも赴かなくてはならないし、医療機関を管理しているので、消耗品は購入していかなければ病院は成り立たない。ガソリンは日本と同じくらいの値段であり、3万円じゃガソリン代にもなりませんよ!?仕方なしに、Directorがポケットマネーから支払うこともある・・・という状況なのです。
切実に、GHS has no money…ということで、JICAに支援を要請することになった。
GHS Office
JICAにはボランティアの活動支援の一環として、「現地業務費」というものがある。
原則として、協力隊の活動は現地の配属先が負担することになっているが、発展途上国においては、うちのGHSのように適当な予算が配分されていない等、経費を負担できないケースがある。そのような場合に、隊員の申請により、JICAが必要性と妥当性を検証した上で支給される。
独立行政法人とはいえ、JICAは国の機関と同レベル。そう簡単にはお金は降りない。でも頑張ってみることにした。
今週は企画書を書き直し、予算見積書を作成した。来週、事務所に提出する予定。
しかし、ここで問題なのが、予算の内訳。
ガーナでワークショップをすると何に一番お金がかかるか?
それは、
①参加手当
②交通費
③リフレッシュメント(昼食とおやつ)
日本でワークショップと言えば、参加者がお金を払ってまで参加し学びを得るもの。
ガーナは逆。主催者側が参加者に参加手当と交通費を払って来てもらい、さらには昼食とおやつまで用意しなければならない。接待ですか??って感じだけど、こうしなければ誰も参加しない。いくら勉強できるとは言っても、ワークショップに参加するためには町まで行かなければならず、交通費がかかる、町へ出たらご飯も買って食べなければならない、そんなお金使うくらいなら行かなくていいよ・・っていうのが途上国の現状。
貴重な経費のほとんどは参加者の懐と胃袋に収まってしまう。
さてはて、JICAがそんなものに支援経費を支給できるのか。。
原則できない。と思う。
でもここで何十年と続くガーナの体制から立て直そうなんていうのは全く不可能な話で、お金が降りないなら、ワークショップは開催できませんね・・・というお話になる。経費のほとんどは後に残らないものではあるけれど、参加者がワークショップで学び、その後それらを地域住民にフィードバックし、それが地域保健の促進につながれば、このワークショップはそれだけのお金をかけて実施した意味のあるものになると思う。
この状況をJICAが考慮してくれるかどうかは分からないけど、とりあえず申請してみよう思います。
でもこれでお金がもらえなかったら、配属先スタッフのJICAのイメージはガタ落ちだろなぁ・・それが怖い(>_<)
ガーナの面積は日本の2/3ほどで、観光名所もそんなに多いわけではないけど、世界遺産とされているお城や素晴らしい自然がある。
また北部と南部で気候が違うのも面白いところで、今回は最北のブルキナファソとの国境から大西洋海岸のビーチまでガーナを横断したので、気候の違いを肌に感じ、それぞれの気候によって生み出される自然を満喫。
北部はサバンナ気候
比較的南部にある私の任地から車で北上すると、だんだん緑が少なくなり、砂の見える面積が大きくなり、そのうちバオバブの木が見られるようになる。
北部でよく見られるお家、通称きのこハウス
ガーナのグランドキャニオンと呼ばれるNakpanduri
「アフリカだー」と実感できる壮大な景色が広がっている。
ブルキナファソとの国境の村Paga
ワニも見れる。
今度は南部、熱帯雨林気候
椰子やマングローブなど熱帯植物の森が広がり、北部に比べるととってもジメジメ・・でも雨が降るのは嬉しい。
コートジボアールに面するWestern州のAxim
ガーナの海は波がとても高く、青というよりは緑っぽい。
長~く続く水平線の先には南米大陸があると思うと、改めて自分がアフリカにいることを実感する。
小さな漁村からカヌーでマングローブの森を抜けて川を上っていく。
ガーナ全土から集められた人々を奴隷として輸出する奴隷貿易に使われたCape Coast Castle
数日でガーナを駆け巡るのはなかなかハードだったけど、楽しい旅でした
日本から来てくれた彼氏も、良い思い出ができたんじゃないかな~
今年に入って、小さなきっかけから、孤児を支援しているNGOとつながりができた。
教会の牧師さんが青年ボランティアと一緒にやっている小さなNGOではあるけど、2週間に1回、その村にいる孤児たち20人を集めて、食糧や衣類、文房具などを提供したり、一緒に遊んだりしている。
先月から彼らのミーティングに混ぜてもらうようになり、「Mama Aya」とか呼ばれている。
牧師さんの希望は、孤児院を設立すること。
今、子どもたちは親戚や祖父母、知人などの家で生活をしているらしいが、十分な食料がもらえなかったり、面倒を見てくれる人が高齢であったりと様々な問題があるそう。社会的に弱い立場に立たされている子ども達を集めて、一緒に面倒を見たいが、まず経済的な問題があり、実現にはほど遠い。土地代、建築費、人件費・・・たくさんのお金が必要になる。孤児院での共同生活を送ることで生じてくる問題もあるだろうし、現在子ども達が、実の親でないにしろそれぞれの家族があり、居場所があるのなら、あえて家族から引き離し、孤児院を設立する必要もないのではないかとも思うけど、きっとまだまだ私にはわからない事情がたくさんあるんだと思う。
牧師さん↓ お米を配っているところ↓
今の私にできることと言えば、子ども達にお菓子を買って行ってあげることくらいで、Financial Problemを相談されても、自分の貯金を使う以外になかなかお金を工面するのは難しい。きっと日本円でそんな高額じゃなくても、こっちの通貨では大金。一時の支援としてお金を提供することは可能だと思うけど、果たしてそれをすることが彼らにとって良いのかどうか。NGOなど支援団体を見つけることができれば、話は進むのかもしれないけれど、私がガーナにいるのはあと1年3か月で、今後もずっと資金援助をしていけるというわけではない。
当面は子ども達の顔を見に行くだけの「国際交流」になりそう。
***************************
普段GHSで行っている活動は、どちらかというと「誰かに求められて」というわけではなく、9ヶ月間自分で模索してきた結果の「これだったら自分ができそう。ひいては現地の人のためにも少しはなるんじゃないか」という活動。協力隊は戦争や難民キャンプのように緊急支援が必要な場所に行くわけではなく、一般の人が営む日常生活の中に入るので、日本にいた時に想像していたような「これをやってほしい、あれをやってほしい」っていうことはない。そんな毎日の中で、時々「これをやってほしい、あれが欲しい」と求められる援助。しかし、お金の問題であるほとんどのそれらには、なかなか応えられない現実。
国際協力って、国際援助って、何なんだろう。
一緒に結核の仕事をしている同僚のお母さんが亡くなったので、お葬式に行ってきた。
同僚といっても、59歳のオジサマのお母さんなので、なんと100歳の長寿だったそう。
一緒に働いているDisease controller↑
ガーナのお葬式は、亡くなって1週間後、2週間後、7週間後、1年後に行う。(亡くなった年齢によりこれより増えたり減ったり・・詳しくはよく分らない。。)お葬式の規模も年齢や家柄によって異なる。このあたりは日本の法事なんかと共通するものがある。
でも雰囲気は全く違う。日本のお葬式と言えばしんみりした感じだけど、ガーナのお葬式は、会場の真ん中に故人の写真を飾り、その周りをぐるっと人々が囲んで座る。家族という単位をとても大切にする文化であり、そして大家族なので、来訪者は列を作って、ずらっと並んだ家族一人一人と握手&挨拶をしていく。日本のように何時から始まって何時に終わるというわけではなく、早朝から始まり夜も遅くまで2日間ほど続く。来訪者は好きな時間に訪問し、居たいだけ居て、帰りたくなったら帰っていくという感じ。music大音量♪、ダンスもあり、ビールやジュースは飲み放題、軽食もあり、とりあえず賑やか。
私も伝統的なものを着た方が良いと言われ、黒い布で作ってみた↓
次は、ぜひ結婚式にお呼ばれされてみたい~
最近、地面によく綿が落ちている。
ガーナは野良犬がそこら中にいるので、最初は犬の毛が生え変わる時期なんかな~とか思ってた。でも、それにしては抜け過ぎ…どんだけ犬がいるのよ!?って思ってた。
この木にたくさんの綿がなっている(表現正しい?)
綿のなる植物と言えば、綿花だけだと思ってたからビックリ~
日本で綿毛が飛べば、すっかり春でポカポカ穏やかな陽気♪っていう感じですが、、
今こっちは猛暑デス。
汗が絶え間なく流れ、ついでにせっかく塗った日焼け止めもすぐに流れ、水分摂取量もどどーん!と増加。水が必要なのに、雨が降らないから水がなくなる。井戸からせっせと水を運んで生活用水を補充。少々濁ってようが、虫が浮いてようが、そんなのあんまり気にならなくなってきた(^^;
乾季の中でも、3~4月がもっとも暑い時期と言われ、この時期さえ乗り越えれば・・今が正念場!!
私の任地は南部の方だから、北部の隊員さんに比べたらまだマシなんやけどね。。でも暑いもんは暑いんですよ・・