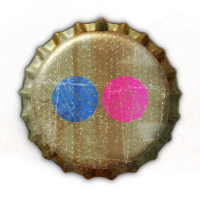「ホテル ルワンダ」を観た。
小学校高学年の頃、ルワンダという国で紛争をやっていたということは、なんとなく記憶にある。でも詳細なんて全然知らなかった。私にとっては、遠い異国の非現実的な物語だった。
この映画を観るまでは・・・
最後のエンディングで、こらえていた涙があふれてきた。隣で見ていた人は号泣していたけど・・・
たった10数年前に、同じ地球上で、こんなことが起こっていたなんて想像もできない。でも本当のこと、1994年に起こった真実の出来事。実際はもっとこれ以上に酷かったのかもしれない。
ナチスドイツの大領虐殺を真似て行われたというルワンダの大虐殺。先進国に操られたアフリカを象徴するような紛争。小手先でアフリカを貪り、このような惨事を招いた先進国は、素知らぬふり、というかあまり知らされてさえいない現実。
私が行くアフリカは、ほとんどの国が先進国によって植民地にされていた。今、アフリカに根強く蔓延っている「貧困」の多くは、先進国によってもたらされたものだという。
自分はアフリカの大地に、どのような顔をして立てばいいだろう・・・と思う。
昨日、3月6日はガーナ共和国の独立記念日。
ガーナはアフリカの中で最も早く独立した国であり、独立してから半世紀経った。
HOTEL RWANDA公式HP http://www.hotelrwanda.jp/
春休みだからか、若い子たちがすごいたくさん居て、すっごい込んでた。おばちゃんのちょー適当な指示に従いつつ、なんでこんなに待たなきゃならんのだ・・・と思いつつ、2時間くらい待って、ようやく免許証をもらってきた☆やっぱり写真はいつもながら無愛想な表情だった・・・もう少し写真写りよくなりたい。。
まぁ、でもこれで、とにもかくにも大型以外の二輪に乗れるわけだっ!!
絶対うまくなって、いずれツーリングとか行ってやる!!
3/4、名古屋で市民公開シンポジウム「エイズとの闘いーその最前線2007」が開催されたので、行ってきた。
1部「エイズの臨床」、2部「エイズの社会学」
薬などかなり専門的な話だったが、薬剤耐性ウイルスの出現など、知らなかったことも聞けた。
2部は「社会学」というほどの内容ではなかった気もするが、1人の先生の講演はなかなか良かった。
日本(主に話は東海地区のこと)では、特にMSMの人の感染が増加している。名古屋は東京や大阪のように、陽性者の支援体制がまだ確立されていないようだが、NGO活動を中心に体制づくりを進めているそう。住んでいる地域のことなのに、全然そういうことは知らなかった。。
また、20代女性の感染も拡大しているのも日本の特徴。私も20代女性。HIV検査だって、受けたこと無かった私。火曜日に受けに行く予定だが、自分がエイズ対策をしにいくのに・・・やっぱりこの問題は他人事ではないんだと思う。
この研修は、主に村落開発普及員の人が受けるもので、エイズ対策からも3人居残りで受けていた。全員で40人以上は研修生がいたが、私以外の人は皆5日間みっちり研修なのに、私はなぜかたった1日だけの指示。それ以外は受けるなとの注意書きまであった。。。
①村落開発とプライマリ・ヘルスケア
講師は丹野かほる先生(新潟大学医学部保健学科国際看護学教授)。プライマリ・ヘルスケアとは、ヘルスプロモーションとは、という大学の授業でさんざん覚えさせられた内容だった。まぁ良い復習にはなったんだろうか。先生は20数年まえ、協力隊員として活動されてたそうで、その頃の話は興味深かった。助産師として派遣され、現地の母子センターやハンセン病病院での活動など、日本じゃドクターしかできないようなことまでやっていたそう。すごーい!と、この時はまるで他人事のように聴講していた。
②隊員OVの経験と知識「異文化での活動」「活動の現場」
村落開発普及員として派遣されていた4人の方の経験談と質問コーナー。
別にわざわざ研修でやらなくても懇親会とかでやればいいんじゃないの?という内容だったけど、まぁいろいろ気になっていた細かなことを聞くことができた。
帰り、JICAのスタッフを突っ捕まえて、ずっと疑問だったことを聞いてみた。
私「なんで私だけたった1日の研修なんですか?この1日を受けることに何か意味はあるんですか?」
J「この研修の指示は2次試験の面接官が決めてるんですよ」
私「今日だけってことは、多分午前の講義を聞かせたかったってことですよね。私は助産師の資格持ってるので、知識として講義内容にあったことは持ってると思うんですけど、っていうことは、つまり丹野先生のような活動をすることがあるってことですか!?」
J「その可能性もあるってことですね。まぁ、知識を復習しておいてもらいたいというのもありますが」
私「・・・・!!!!!!!!」
私はエイズ対策隊員です!!
専門知識を持って活動をしたいとは思ってるけど、技術をアフリカで実践なんて思ってもいないんですよーー
助産師の資格持ってるって言ったって、日本では主にNICUで働いていたわけでして、お産なんて、働き出してからは数例しかとってないんですよ。。丹野先生みたいに、赤ちゃんのルートをとったりとかも、日本じゃドクターしかしてないんですよ。。しかも現地は日本のように物品がそろっているわけでもない・・・
んなこと、私に求めないで~~~!!
とはいえ、、、
資格を持っている以上、何かあれば、逃げる余地がなければ、私がやるしかない場合もあり得る。現地では無資格の人がやってるんだから、いざとなれば私がやらざるを得ないかもしれん。。
焦ってきた・・・
どっか、見学だけでもさせてほしいと思い、大学の先生にフリースタイル分娩をやっている病院はないかとか聞いてみた。とりあえず今日できることは・・・現地に持っていくために、通販でビニール手袋とアイソレーションマスクを注文した。。
今日でついにエイズ対策技術補完研修は最後。
とっても早かった。。もうちょっと研修したいというのが本音。
①ブラジルのエイズ活動の事例
講師は元JICA母子保健プロジェクト専門家、現東海大学助教授(国際学)の小貫大輔先生。
ブラジルはエイズ対策がかなり進んでおり、エイズに関しては最先端である。HIV検査率も成人は50%に及ぶ。日本なんてほとんどの人がHIV検査の存在すら知らないんじゃ。。。日本はエイズに関しては超後進国。セルフヘルプグループと協力してやっていくと良いらしい。
とにかく熱い、情熱たっぷりの先生だった。ちょっと話が抽象的でよく分からんところもあったけど、印象に残っている言葉↓↓
エイズの問題はsexと死の問題、「愛」と「死」を外しては考えられない。(注;エイズ=死ではない)
ローカルな毎日の活動がググローバルにつながっているんだという意識が大切。
相手を変えようと思うなら、まずは自分が変わらなくてはならない、相手に影響を及ぼすほど自分という存在がゆらいでいく。
自分の立ち位置はドコか考える。
②タイエイズ教育手法の紹介と実践
SHAREの活動から。
1、HIV感染リスクカードの並び替え
2、水の交換
14人が一人1つずつカップに入った水を持ち、制限時間内で水を少量ずつストローで吸い上げ、交換する(水の交換=性交渉)。実はその中の1つに水酸化ナトリウムが含まれており、HIVがどのように拡大していくかを示すというもの。水酸化ナトリウム入りの水はフェノールフタレイン液を垂らすと赤く変色する。
私は制限時間内に水を3人と交換したが、一番最初の人が水酸化ナトリウム入りだったらしく、3人としか関係を持っていないのに感染していた。水酸化ナトリウムが入っているかどうかなんて見た目には分からない。HIV陽性である人も見た目には分からず、どうやって感染していくかも見ただけでは全く分からないということ。
3、コンドームの装着練習
バナナの中に男性のペニスの模型が入っていた(笑)正しい装着順序、実際に正しく装着できるかなどを実施。私のグループは男性3人、女性2人だったので、ちょっと恥ずかしかった。その上、皆の前でデモをやることになってしまい、男性がペニスを持ち、私がコンドームをつけた。。
恥ずかしいために、あいまいな表現になってしまうことが日本ではよくあるが、そのあいまいさ故にうまく伝わってないこともある。英語ではあいまいな表現なんてできない。うまく伝わらないければ、教育している意味がない。実際にコンドーム練習に親指を使って実践していたため、性交渉のときには親指にコンドームをつけてやれば妊娠しない、STI予防になると信じていたという例があるらしい。笑ってしまいそうな話だが、何の情報も持たない人の前では、それが信じられてしまうんだから、“伝える”ということは慎重にやらないといけない。
4、話し合うスキル
3つのシチュエーションで、コンドームをつけてほしいと切り出すには?を考えた。相手ができるだけ嫌な思いをせず、かつ自分の健康を守れる方法で。話すことも1つのスキル。
最後に皆で輪になり、研修の感想を一言。
私は、やっぱり価値観というものを一番考えさせられた。この研修で得たものは、HIVの知識もあるが、それ以上に「自分とは何者か、人とは何か」を考えるきっかけ。今まで踏み込んだことのない世界に足を踏み入れ、少しだけ自分の垣根を下げることができたと同時に、今まで自分が築き上げてきたものが崩れていく。いろんな人の話を聞くたびに、私の土台は揺れている。これからも新しい出会いがたくさんある。きっとその度に自分という人間を振り返らないといけないと思うが、焦る気持ちを押さえて、倒れない程度に揺らぎながら、少しずつ土台を固めていけばいいんじゃないかという現段階での結論。
新幹線を降りて、名古屋駅に着いたとき、いつもは都会だと思う名古屋でさえ、ビルがない、人がいない・・・と思った。三重はさらに激しく人がいなかった。。
国家試験帰りの彼氏と名古屋駅で会い、一緒に帰ってきた。
(2/28の話)
①タイを事例としてHIV陽性者グループとコミュニティでの参加型啓発
今回の研修を企画、主催してくれているSHAREのタイでの活動紹介。大学1年の時に参加したカンボジアスタディツアーでSHAREの活動を垣間見る機会があったが、タイのエイズ対策にもとても力を入れている。
1つ、疑問がフツフツ・・・
母子感染予防をするために、日本なら
①妊娠期からウイルス量を下げるため抗エイズ薬を内服し、
②分娩は帝王切開(経膣分娩によるベビーの血液暴露を防ぐ)、
③生後一定期間はベビーにも内服させる、
④完全人工栄養 などを実施する。
しかし!!途上国の場合、①③薬が手に入らない、②帝王切開をできる設備、人材がいない、④粉ミルクは高い、手に入ってもミルクに使われる水が不衛生であるため、下痢などで赤ちゃんが死んでしまうため、母乳の方がまだ安全、という。
んじゃ、一体どこで母子感染予防をするさ???
私の要請内容には“母子感染予防”という言葉がちらついているが、私は何ができるんだろう・・・HIV陰性母からもらい乳とか、母乳を煮沸とか、いろいろデメリットも大きいが、命には替えられないという方法もあるっちゃあるけど。。
②アフリカのエイズ活動の事例
JOICFPの活動紹介、講師は角井信弘先生。JOICFPはガーナ、クマシ周辺でも活動を行っている(PPAG)とのことであり、現地に行ってからも関わっていくことのできそうな団体。VCTの理想モデルATOMMの説明はなるほど納得。
6つの村の人に絵を描いてもらったという紙芝居はなかなか素晴らしいものだった。たかが紙芝居、されど紙芝居。かなり使える媒体のようだ。ちょっと紙芝居なめてた・・・
③途上国コミュニティでのプログラム立案に関する参加型ワーク
私達に言い渡された要請内容と実際に現地で待ち受けている要望には、大きな差があることが多いらしい。エイズ対策!と意気込んでいってみたら実際は、どこがエイズと関係してるんだろう・・・何しに来たんだろう・・・と凹むことがよくあるらしく、それに備えたワークショップ。
協力隊員側と現地スタッフ側に別れ、それぞれに与えられた問題を考える。私は現地スタッフ側、地域の問題は「スラムに住むHIV女性団体が作った民芸品が売れなくて、借りていた資金返済ができない」というもの。協力隊員に期待し求めたものは、販路開拓、資金援助、上層部や他団体との交渉などだった。一方、隊員側はエイズ対策、啓蒙活動をする気満々でやってきた。双方の要望にズレがあるため、初対面からつまずくという設定。隊員としては、自分達は人材、技術派遣であり、資金援助をするわけではないのに、日本人=リッチというイメージから金をたかられる。これは実際によくある話だそうだ。私は現地スタッフ側だったが、数ヶ月後のわが身を見るようで、苦笑い・・・しかもこれを英語もしくは現地語でやりとりしなきゃいけない。。あーできるんかなぁ・・・
研修もあと1日。明日は飛行機の時間などもあり、皆時間がないので、今日打ち上げ。赤裸々にいろいろ話し、楽しい時間となった。