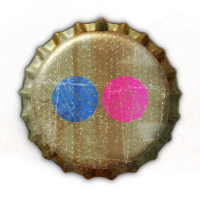今年1月、うちの郡のHIV陽性者グループがJICAの援助を受けて始めた石鹸作り。2月以降は自分たちだけで続けていくことを目標にしているが、1月の2日間でかなりたくさんの石鹸を作ったので、先月のミーティングまでにはそれら全てを売り切ることができなかった。そこで先月のミーティング時には、今月のミーティング時までに売り切り、全員がお金をバックし(売上の一部は本人に収入となる)、2回目の石鹸作りを実施しようと話し合っていた。
そして、先週木曜日が今月のミーティングデー。何事もなかなかスムーズには進まないガーナ、何となくそうなる予感はしていたが、やっぱり今月も実施できず。。
主な理由は2つ。
①お金を全額バックできていない人が多い。
②今回のために購入したソーダの質が悪く、返品交換に時間がかかる。
私がここにいられる時間ももう限られているので、少しがっかりしたが、ガーナに来て、諦めるのが早くなったと我ながら思う。できないものはできない、仕方ない。でも、きちんとお金を支払って、次の石鹸作りを待っているメンバーもいるので、このままウダウダと待っているわけにはいかない。
担当スタッフと話し合い、今後の予定を計画。
①以前お世話になったインストラクターを通して、質の良いソーダを手に入れる。
②まだお金をバックしていない人は、直接訪問してお金を徴収。
③次回のミーティング時に石鹸を持ち帰れるように、次回ミーティングまでにメンバーを集め、石鹸作りを開催する。
④前回から時間がたっているので、インストラクターに再度立会いをお願いする。
計画は計画。計画通りに行くとはいう期待はしない。でも、この活動を続けることができなければ、1月にJICA援助を要請した意味がない。私が帰国するまでに1回くらいは自分たちで石鹸作りをやってほしいなぁ…というのが正直なところ。
ラベルがあった方が売れる!というので、石鹸のパッケージにいれるラベルを作成してみた。外国人効果を狙いたいという本音もあるらしく、どうしても私の顔写真を入れろ!というので、私もどうしても1人じゃ嫌だ!と、他のスタッフ2人も巻き添えにしてみた^^;
ちょっと恥ずかしいけど、早くこのラベルが使われる日が来ますように~
先週末はホストファミリーの家に遊びに行き、いつものようにフフをご馳走になり、食べすぎて動けない…!!ほど食べて、ソファでパパのIsraelとダラダラしていた^^;
すると、横でママのVeronicaと姪のSandraが豆乳アイス作りを始めた。豆乳、小さい頃はあんまり美味しくないのに、体に良いからと親に無理やり飲まされてた気がするけど、大人になってから結構好きになった。ガーナでも豆乳は買える。でも、とても甘い。最初はおいしいのだけど、やっぱり甘すぎる。ホストファミリーが作るものは、ホントにローカルなもので、彼らはこれを凍らせて、アイス?シャーベットにして売る。ママは小学校の先生なので、学校で子ども達に売っているらしい。日本じゃ、先生が生徒相手に商売するなんて考えられないけど、ここじゃ普通。
大豆を粉にしたものと水を混ぜる。
よく混ぜたら、それを濾す。
すると、ミルクのようなキレイな白い液体に。
それをしばし沸騰させ、砂糖を大量に混ぜる。
冷まして、袋詰めすれば完成。
私としては凍らせずに、そのまま豆乳として飲みたいところだが、やっぱりと~っても甘いので、甘さ控えめ豆乳は自分で作るとして、これはシャーベットにして頂きます★
日本でも大豆の粉って手に入るのかな…?
私は平成19年度1次隊としてガーナに来ており、私の同期は10人いる。理数科教師4人、小学校教諭1人、コンピューター技術1人、看護師1人、保健師1人、栄養士1人、そして私エイズ対策1人。
ガーナで最後の19-1全員集合(1月)
うち、理数科教師と小学校教諭の2人が現職教員での参加。4月から始まる新学期に合わせて職場復帰するため、3月20日に通常より3か月早い帰国となる。
先日、彼らの帰国報告会があった。2人とも一生懸命2年間やってきたんだなぁということが本当によく伝わる報告で、そして同期だから思い入れも強く、感動してしまった。やっぱり一緒に訓練を受け、一緒にガーナに来て、同じ2年を過ごしたというのは大きいとしみじみ思う。実際にガーナにいる時は、任地もバラバラ。そんなに会う機会というのは多くないし、人間関係いろいろありはするが、頼れる存在はやっぱり同期だし、そんな同期が2人も帰ってしまうのはやっぱり寂しい。
帰国する2人と
私もあと3か月後には帰国となり、すぐに彼らの後を追うわけだから、今度は日本での再会を楽しみに、それぞれがそれぞれの場所で頑張ろうと素直に思えた、しばしのバイバイでした。
先日、携帯に知らない番号から電話がかかってきた。相手はTwi語しか話さず、そして興奮していて何を言っているのか分からない。たまたま病院にいたので、英語の話せるスタッフに通訳してもらった。
相手は、先日夫に追い出され、今は1歳の娘と2人で暮らしているHIV陽性者の彼女。彼女は電話を持っていないため、近くで働いていた大工さんの電話を借りてかけてきた。
空き巣に入られ、所持金を全て盗られた…と。
彼女が住んでいる部屋は、建設途中で止まっている窓も屋根もない家。そんな所に入る空き巣がいるのか?と思ってしまうが、鍵もカンと一発やればすぐに壊れてしまう小さなもので、私でも入ろうと思えば入れてしまう程の侵入しやすさ。そんなに大金がないのは承知で入ったのだろう。
その日の夕方、彼女宅を訪問し、家の状況を見せてもらった。被害に遭ったのは、鍵のかかったカバンに入れていた彼女の全所持金32GHC(うち、10GHCは他人から借りているもの)、水筒など日用品の3点。
電気も水もない、暗く狭い彼女の家
ビニールシートをかぶせただけの屋根
彼女は今、なんとか仕事を得て、ココと呼ばれる食べ物を売って生計を立てている。雇われて、商売をしているので、彼女の元に入る収入は1GHC/日(約100円)。そこから、自分と娘の食費や生活費を支払い、少しずつ貯めてきた22GHC。最初は怒りで、勢いの良かった彼女だが、だんだん声が小さくなり、気がつくと泣いていた。自分がHIVに感染していることを知った時も、夫から暴力を振るわれた時も、そして夫に家から追い出された時も、仕事がなくて本当に困っていた時も、他人に涙を見せることのなかった彼女が、初めて泣いていた。いつも1歳の娘をおぶって、いつも肩を張って頑張っている彼女だが、今回の件で今までこられていた涙があふれてしまったのだと思う。
私にできること。お金をあげることは簡単。協力隊員は約400$/月ほどの生活費をJICAから頂いているので、彼女が失った32GHC(約3200円)は「ハイ、どうぞ」とあげることのできる額である。きっとあげたら彼女は喜ぶに違いないし、その分彼女の負担も軽くなるかもしれない。でも、彼女がこの数か月必死に歩き、得た仕事で貯めたその額を、いとも簡単にさらっとあげることはできなかった。かと言って、何も助けてあげないわけにはいかないので、5GHCだけ手渡し帰った。
彼女の家の前から
お金をあげることはとても簡潔、そして難しい。あげるのは簡単だし、あげたい気持ちはある。でもあげて終わりじゃない。その後も付き合っていかなければならないし、相手の厳しい生活環境は変わらない。ヘルプできる立場にいながら、手を差し伸べないのはおかしいだろうか?
私は一体どこに立っていれば良いんだか揺れてしまう。
最近うちに住みついているネコが子猫を産んだ。3匹。
かわいい(><)***!!!以外に言葉がナイ!
ある朝、キッチンに行ったら、3匹がガスボンベの裏で縮こまっていた。かわいい(><)
ケド、キッチンは困る。。ということで、なんとか外に行ってちょーだい作戦を開始。
パンとミルクでつってみる。つられて、パンを食べに来るにゃんこ♪ 可愛い…
でもミルクにたどり着く前にお腹いっぱいになり、またガスボンベの裏に戻ってしまい失敗。
ミルクをもっと手前に置いてみるとかしてみたけど、また失敗。
こっちもお仕事に行かなきゃならないのよ…ということで、結局チリトリで追い回して外に出すハメに^^;
「ごめんね」の印に、最近ミルクを置いてます。外にだけど。
いやぁ、可愛い☆★☆
病院、各ヘルスセンターでは、村を5~6か所決めて、毎月1回出向き、体重測定と乳児健診を行っている。私も月に2~3回、それに同行するようにしている。
村に行くのは、ヘルスセンターの中で働くよりも、新しい発見があって新鮮。見たことない果物や花を見つけたり、人々の暮らしを身近に感じたり、アフリカの貧しさを目の当たりにしたり。
健診のお手伝いをしている村のヘルスボランティア
家庭訪問をする時もある。
先日、フィラリアの患者と出会った。足がパンパンで、まるで象のようになっている。彼女はもう10年以上前から患っているという。痛みはひどくなる一方だが、お金がないため病院に行くことはできない。
フィラリアは寄生虫の1種で、蚊などの吸血昆虫を媒介する熱帯感染症。病気が進行すると、フィラリアがリンパ管を破壊するので、末梢組織の循環が阻害され、彼女のようなひどい浮腫をきたし象皮症となる。
治療は外科的治療と内科的治療があるが、ガーナで治療を行うととても高額になる。何か事情があって、電気も水もないボロ屋にまだ学生の息子と住んでいる彼女に、とても払える額ではない。
とりあえず出来ることと行ったら・・・対症療法。
足を冷やす、石鹸でよく洗い清潔にする、マッサージする、寝る時は足を高くする。こんな些細なことしかできないが、やらないよりはマシだと思うので、石鹸(1日100円以下の生活をしている人たちにとっては、1つ50円の石鹸でさえ買えなかったりする)を持って彼女を再訪した。
うちの郡の助産師さんを対象にした新生児蘇生ケアのワークショップが開催された。私も一応、うちの郡で働く助産師なので出席。
内容は新生児出生時の蘇生ケア。けっこう高度な内容で、プロトコル化された一連のケアを勉強した後、正常、異常の判断の仕方、アンビューバッグの使い方を中心に学んだ。(今はアンビューバッグとは言わないらしい。Self-Inflapping Bagと言うのだそう。日本でもそうなったのかしら…?)
ワークショップ前後に同じテストを行い、どれだけ知識が深まったかを確認した。英語のハンディは別としても、NICUで働いていた経験のある私でもちょっと難しいなぁと思う内容だった。それにしても講義中は珍回答続出で面白かった^^;いや、本当は嘆かなければいけないところだろうが、ヘルスセンターの管理職についている助産師でさえ、新生児の正常な呼吸回数を100回/分と答えたり、呼吸状態が良くない場合の刺激の仕方の1つとして、ベビーを冷たい水につけると答えたり…。でもほとんどの人がワークショップ後には、難しいテストの点数が上がっていたので、学びは大きかったと思う。
うちの郡の病院、ヘルスセンターではアンビューバッグどころか、酸素さえまともに使えていないのだが、このワークショップ後、アンビューを各施設に置くとのこと。本当か^^;?酸素がなくてもバッグがあれば、今までより少し高度な蘇生ケアが期待できるカナ~と思うが、それなら吸引機とサクションチューブも欲しいところ…。ま、でも高望はせず、先日、新生児用聴診器の寄付もしたので、それと合わせて今までほとんど行われていなかった新生児ケアを見直してほしいなと思う。